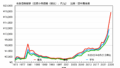今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問33です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 33】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条に規定に違反する。
2. 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自ら貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合におおいては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
3. 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完成前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
4. 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初の広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
解説 宅建業法(広告等)
1. ◯ 正しい。契約が成立した物件はもう他の人は取引できないのですから、当該広告をインターネットに掲載し続ける行為は「虚偽広告」や「おとり広告」になりかねません。法律を知らなくてもこれが正しいと想像できると思います。 法第32条(誇大広告等の禁止):宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
2. ◯ 正しい。基本問題。自ら貸主になる貸借(転貸を含む)は宅建業法の「取引」の対象外なので、法第34条の規定に違反しません。 法第2条(用語の定義)第2号を参照。
3. × 誤り。基本問題。造成工事云々と書かれていますが、取引態様の別は必ず明示しなければなりません。 法第33条(広告の開始時期の制限)、法第34条(取引態様の明示)を参照。
4. ◯ 正しい。基本問題。次回以降の広告を初めて見る人もいるはずなので、本肢が正しいことは容易に想像できると思います。 法第34条(取引態様の明示)を参照。
本問はサービス問題。こうした問題は受験者のほとんどが正答できるはずなので、取りこぼさないよう試験勉強を進めましょう。