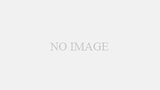今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問2です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 2】 個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
2. ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
3. ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
4. ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
解説 連帯債務と保証債務
1. × 誤り。①(連帯債務)も②(保証債務)も、書面又は電磁的記録でなければ保証債務契約の効力を生じません。民法第446条(保証人の責任等)第2項、第3項を参照。 お金が絡む契約が口頭でも有効な訳が無いだろうと気づけば、本肢は「×誤り」だと推察できるサービス問題。
2. × 誤り。①と②の催告の抗弁権が逆です。①(連帯債務)ではAはまずCに請求するよう主張できません。民法第454条(連帯保証の場合の特則)を参照。一方、②(保証債務)ではAはまずEに請求するよう主張することができます。民法第452条(催告の抗弁)を参照。 連帯保証って片方に支払い責任を押しつけられるやつだと知っていれば、本肢は「説明が逆」だと推察できるサービス問題。
3. ◯ 正しい。令和2年の民法改正で、①(連帯債務)は極度額を定めなければ保証契約自体が無効になりました。②(保証債務)は居住用建物の売買契約に対しての保証であり債務額が増える心配がないので、極度額を定める必要はありません。民法第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)を参照。
4. × 誤り。①(連帯債務)も②(保証債務)も、保証人が債権者に履行情報提供を請求したら、債権者は保証人に対し遅滞なく履行状況を提供しなければなりません。 民法第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)を参照。 保証人が最も気になるのは債務者の返済状況であり、それを債務者に確認しても嘘をつかれる可能性があるので、債権者に確認するのが確実だと考えて、本肢は「誤り」だと推察した受験者は素晴らしいです。
本問は連帯債務と保証債務からの出題。宅地建物取引契約(売買・交換・貸借)で必ず登場する内容なので、しっかり勉強していた受験者にとっては容易に正答できたと思います。しっかり勉強していなくても、肢1と肢2は誤りだと容易に気づくサービス問題だったので、正解は肢3か肢4の実質二択だったと思います。