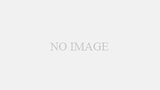今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問4です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 4】 AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
2. Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
3. Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
4. Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
解説 担保物件
1. × 誤り。「不動産に…質権を設定することはできない」部分が誤り。不動産にも質権を設定することはできます。 民法第356条(不動産質権者による使用及び収益)を参照。
2. × 誤り。「留置権を行使することができる」部分が誤り。本件契約は、BがAから預かっている動産に関して生じた債権ではないので、留置権を行使することはできません。要は「これとそれは別問題」というやつです。 民法第295条(留置権の内容)を参照。
3. × 誤り。本件契約(金銭消費貸借契約)は、先取特権を行使できません。一般の先取特権は「①共益の費用、②雇用関係、③葬式の費用、④日用品の供給)によって生じた再建にのみ適用されます。 民法第306条(一般の先取特権)を参照。 TVドラマなどで消費者金融業者が債務者に嫌がらせしてでも金銭回収しようとするシーンを思い出して、「金銭消費貸借契約で返済滞納しても家屋を差し押さえられない」ことを推察できた受験生は、素晴らしい応用力です。
4. ○ 正しい。ひっかけ問題。不法行為により発生した債権を自働債券(相殺を申し込むA側の債権)として相殺することはできます。なお逆に、不法行為により発生した債権が受動債権(相殺を申し込まれるB側の債権)である場合は相殺できません。 なお民法第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)を参照。
本問は難問。担保物件からの出題ですが、正解肢がひっかけ問題だったので、正答できた受験者は少なかったかもしれません。担保物件には法廷担保物件(留置権、先取特権)と約定担保物件(質権、抵当権)の4種類があり、特に抵当権は毎回のように出題されます。しっかり勉強しておきましょう。