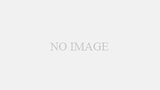今日のネタは「勝手に買物アドバイス」シリーズ。第5回は扇風機。
扇風機は風を発生させる家電製品。様々な種類がありますが、風を体に当てて涼を得る「扇風機」、室内の空気を循環させる「サーキュレーター」を区分して呼ぶことがあります。
扇風機の仕組みはどれもほぼ同じで、モーターで羽根を回して風を発生させます。羽根の形状、モーター、風量・風向き微調整など様々な工夫が凝らされています。具体的には、
1. 羽根:軸流ファン(プロペラファン)と貫流ファン(クロスフローファン)に大別されます。軸流ファンは飛行機のプロペラのような形で、長所は大風量で比較的静かなこと。短所は遠方ほど風が広がり弱くなることです。貫流ファンは円筒形で、エアコン等に内蔵されています。長所は風速が早く遠くまで到達しやすいこと。短所は形状が複雑で清掃が面倒なことです。
2. モーター:扇風機には長らく、単相誘導モーター(コンデンサーモーター)が使われてきました。長所は構造が簡単で安価であること。短所はきめ細かい風量調整ができないことです。近年は電子制御で風量を細かく調整できる製品が多く販売されています。電子制御式に用いるモーターは、ACモーターとDCモーターがあります。ACモーターは交流電源を用い、長所はDCモーターに比べて安価なこと。短所は運転音や消費電力が大きめなことです。DCモーターは直流電源を用い、長所はきめ細かい風量調整ができて、運転音や消費電力が小さいこと。短所は価格が比較的高くなることです。
3. 首振り機構:主流はクランク機構で、モーター回転を減速しクランクで左右運動に変換するもの。モーター上部に切替つまみが付いているのが目印です。近年は首振り専用モーターを内蔵し、左右だけでなく上下にも首振りする製品も販売されています。
4. 付加機能:タイマー、ゆらぎ(不連続で自然に近い風量調整)、リモコン、温度センサーで風量自動調整、ヒーター内容し温風も出せる製品など様々な製品が販売されています。
安全上の注意点は、モーターを用いているので、長期使用に伴い異常な壊れ方をすることがあること。扇風機は「長期使用製品安全表示制度」の対象製品で、製品本体等に「製造年、設計上の標準使用期間、経年劣化についての注意喚起」が表示されています。標準使用期間内であっても、異常な音や振動、においを感じたら電源を切り、販売店等に相談しましょう。
特に、リチウムイオン電池を内蔵したハンディファン(携帯型扇風機)は要注意。異常高温に晒したり(夏季の車内など)、強い衝撃を与える(うっかり落とす)と、破裂や発火の危険があります。説明書に従って丁寧に使用し、適切に廃棄しましょう。